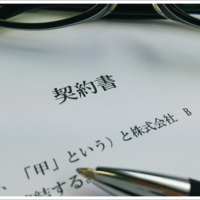知的財産権講座第84回:ここがわかるか?が山の特許法(2)

国内優先権制度
「国内優先権制度」について、説明します。
(特許法41条)
簡単な事例を元に説明します。
基本的な発明について特許出願Aをしました。
特許出願A:特許請求の範囲a/明細書b
さらにその後、技術的改良の発明が生まれました。
後から発明の内容を修正したい場合、補正という
手段があります。
しかし原則は、出願Aに記載した以上のことの
追加はできません(17条の2第3項)。
この場合、新たな別の出願をしなければならない
全ての開発、改良が終わった後で、出願しなければ
ならない
それでは、不便です。
そこで、この場合は「国内優先権制度」を利用
できます。
先の出願Aを基礎として、「国内優先権」を
主張して、改良発明の
特許出願B:特許請求の範囲aとb/明細書C
をします。
出願Aと出願Bの重複する部分の特許請求の範囲aに
ついては、新規性などの判断は、先の出願Aの
出願時にされたものとなります。
後の出願Bは、先の出願Aの出願日から1年以内に
出願しなければなりません。
出願人は、この「国内優先権制度」を利用して
包括的な技術全体を特許権利化できることに
なります。
この辺りは、わかりにくいためか、
よく出題されるところです。