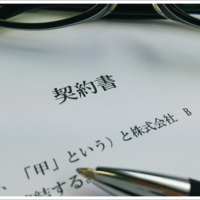知的財産権講座第146回:知っておくと役立つ特許の話

特許権の権利の範囲はどのようにして
判断すればよいのか
例えば、
電機メーカーA社は、液晶TVの技術の特許を
保有しています。
どうやら、最近、電機メーカーB社が発売した
液晶TVは、A社の特許権を侵害しているらしい
ということがわかりました。
A社は、どのようにB社に対応したらよいでしょう。
ここで、まず、確認しておきましょう。
B社の製品が、A社の持つ特許権の「権利の範囲」
に含まれなければ、A社の特許権の侵害にはなりません。
特許権は、発明という技術的思想であり、目に見えない
財産権(無体財産)です。
では、特許権の権利の範囲はどのようにして
判断すればよいのか 解説します。
特許権の範囲は、特許明細書の「特許請求の範囲」
の記載に基づいて定められます。
「特許請求の範囲」で、特許権の権利範囲が
決められます。
原則として、「特許請求の範囲」における全ての
構成要素が含まれている場合のみが、その特許権
の権利範囲に含まれるとされます。
例えば、A社の液晶TVの技術の特許において、
「特許請求の範囲」に、
「Xの材料とYの材料とZの材料を用いた液晶を
使用する液晶TV」と書かれていた場合、
B社の液晶TVが、
「Xの材料とYの材料を使用する液晶TV」であれば、
Zの材料を使用していませんので、A社の特許権
の権利範囲ではないということになります。
特許は、出来るだけ広い権利範囲で取りたいです。
しかし、極端な話で「液晶TV」としても、
権利範囲が広すぎて特許は取得できません。
条件を付けて、
「Xの材料とYの材料とZの材料を用いた液晶を
使用する液晶TV」と権利範囲を限定することで
特許を取得できる場合があります。
条件を付ければ、付けるほど権利範囲は狭くなります。
できるだけ、権利範囲を広く取りたい、しかし
広すぎると特許の取得が難しい場合が多い。
ここで、重要なことは、「特許請求の範囲」を
書く際には、不必要なことを書いて、
権利範囲を狭くしないようにすることです。