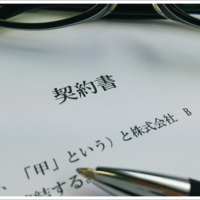知的財産権講座第63回:発明は新規性だけでなく進歩性も必要

発明は新規性だけでなく進歩性も必要
特許を受けるためには、発明は新しいもの
でなければなりません(新規性)。
しかし、発明は新しいだけではいけません
発明には進歩性(特許法29条2項)も必要です。
特許出願前に、その発明の属する技術の分野
における通常の知識を有する者が、前項各号
に掲げる発明に基づいて容易に発明できたときは、
その発明については、同項の規定にかかわらず、
特許を受けることはできない(特許法29条2項)。
発明が新しいものでも、簡単にできる発明は
特許を受けられません。
進歩性がないとされます。
進歩性がないのは、例えば、
TVの外装材として、最適なプラスチック材料
を選んだに過ぎない場合です。
このような進歩性のない誰でも思いつく
発明に特許を与えると、特許権が乱立し、
開発や生産などに支障があります。
産業の発達も妨げにもなります。
簡単に発明できたかどうかは、
誰を基準に判断するのか
「その発明の属する技術の分野における通常の
知識を有する者」です。
「当業者」とも言います。
「当業者」は、プラスチック材料の発明
なら、その業界の専門家です。
素人が基準ではありません。
判断基準のレベルは高いです。
発明が進歩性がない。
これは、実務での特許の審査においてもらう
拒絶理由通知の中で多いものです。