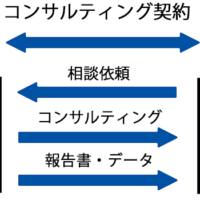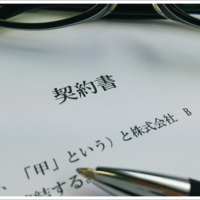知的財産権講座第23回:特許権侵害

2013年11月24日実施の知的財産管理技能検定第16回より2級実技試験
カメラメーカーX社は、特許発明A「新規な合金aを用いて軽量化したボディ
に無色透明なレンズbを装着したカメラ」に係る特許権を有している。
そのカメラメーカーY社が、合金aを用いて軽量化したボディに色つきの
広角レンズcを装着したカメラBを製造販売していることがわかった。
ア~エを比較して、X社の考えとして、適切であるか。
イ 特許発明Aの特許出願手続において、カメラBを特許請求の範囲から
意識的に除外しているか否かは、Y社の侵害行為を認定するにあたり、
重要な判断要素となる。
正解は、○
特許権の効力が、どこまで及ぶのかという、特許権の範囲の解釈の問題です。
原則は、発明を特定する事項を、すべて備えていなければ、特許権の範囲に
含まれません。
しかし、発明者が、これは特許権の範囲に含まれないと主張したことは、
特許権の範囲に含まれません。
この問題では、「意識的除外論」が重要な判断要素となります。
このように書くと、なんだか難しい話のようですが、
自分の権利を主張する際に、自分でこれは権利範囲には含まれないと
主張したことは権利範囲には含まれないと判断されます。
きわめて常識的な話だと思います。
特許権の範囲に含まれなければ、Y社は侵害行為には当たりません。
では、なぜ「意識的除外論」が問題となるのでしょうか?
例えば、特許発明Aの特許出願手続において、X社が審査官から拒絶理由
を受けたとします。
X社は、拒絶理由を解消するために、反論をするときに、これは特許権の範囲に
含まれないと主張するこがあります。
なんとか、拒絶理由を解消して特許権を取りたいですからね。
拒絶理由を解消するために、反論をするときには、後での特許権の権利行使
も考えて、慎重に対処すべきということです。