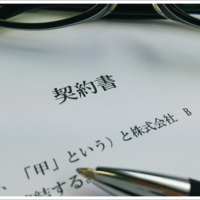知的財産権講座第61回:発明の新規性

特許を受けるためには、発明は新しいもの
でなければなりません(新規性)。
また、気持ちを新たに知的財産権講座をスタートします。
よろしくお願いいたします。
以下のように特許法では、規定されています。
公知、公用、文献公知の3つです。
公知、公用、文献公知の発明は、
新規性がありませんので、特許を受ける
ことができません。
①公知
特許出願前に日本国内又は外国において
公然知られた発明(特許法29条1項1号)
②公用
特許出願前に日本国内又は外国において
公然実施された発明(特許法29条1項2号)
③文献公知
特許出願前に日本国内又は外国において
頒布された刊行物に記載された発明
又は電気通信回線を通じて公衆に
利用可能となった発明(特許法29条1項3号)
注意点は、以下です。
「特許出願前」という判断は、時間で判断されます。
午前中に発明を発表し、午後にその発明を
特許出願は、新規でないとされます。
「公然」は、発明を理解できる人に知られた場合です。
発明の理解できない子供に発明を知られても
新規性は失われません。
また、守秘義務のある人、例えば開発部門
の人が同じ会社企画部門の人に発明を話しても
新規性は失われません。
他の会社の人に、発明を話す場合は
秘密保持契約を結んでいないと新規性は
失われてしまいますので、注意しましょう
「文献公知」
本や、ホームページに発明を記載した場合は、
閲覧可能となった時点で新規性は失われます。
本や、ホームページを誰かが見たという事実
は必要ではありません。