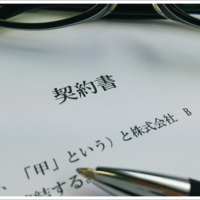相続手続きの流れその13(限定承認)

相続財産のプラスマイナスがはっきりしない場合には限定承認にする
人が亡くなるとその人の一切の財産は相続人に受け継がれます。
相続人が複数いる場合は、全続人が権利・義務を受け継ぎます。
受け継ぐのは、プラスの財産だけでなく、ローン返済などマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産を相続したくない場合は、相続放棄をすることができます。
相続人は、財産を相続する権利はありますが相続する義務はありません。
相続するかしないかの自由があります。
借金返済などの義務(マイナスの財産)から逃れる方法として、相続の放棄以外に、限定承認という方法もあります。
これは、プラスの財産を限度としてのみ遺産を引き継ぐことを承認するものです。
この場合、マイナス分が多くても相続人は責任を負いません。
プラス分が多ければ取得することができます。
相続財産のプラスマイナスがはっきりしない場合にはよい制度です。
限定承認は、場合によっては好都合の制度ですが、次の点には注意しなければなりません。
相続人全員で限定承認をする
相続人が複数いる場合は、相続人全員で共同で限定承認を行わなければなりません。
もし相続人の一人がそのまま相続財産を受け継いでしまう(単純承認)と、他の相続人は、限定承認ができなくなってしまいます。
この点には、注意しなければなりません。
なお、相続人の中に相続放棄をした人がいても限定承認をすることができます。
限定承認は、財産目録を作成して家庭裁判所に申述書を提出することで行います。
限定承認は5日以内に広告する
限定承認をした人は、遺言による財産を贈られた人(受遺者)や亡くなった人の債権者のすべてに限定承認をしたこと、一定期間に請求すべきことを、
5日以内に広告しなければなりません。
広告期間は2ヶ月以上です。
受遺者や債権者との公平を図るためです。
受遺者が、遺産を取得することを当て込んだいたのに、いきなり遺産を取得できないというのは酷ですので、事前にお報せします。
また債権者は、もしマイナス分が多いときには、各債権者に対して、相続財産額を各債権者の債権額に応じて分けます。
すなわち債権額に比例した割合で分けた額(按分)を返済することになります。
これは、相続財産の範囲内で行われます。
したがって、絶対に持ち出しとはなりません。